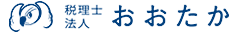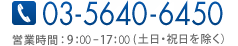相続人が不存在の場合の相続手続き
死亡した人に相続人のあることが明らかでないときがあります。相続人のあることが明らかでないときとは、相続人となるべき人が戸籍上見当たらない場合のほか、相続人全員が相続の放棄をした場合、あるいは相続欠格や推定相続人の廃除により相続資格を失っている場合も含まれます。
なお、戸籍上相続人はいるものの、その相続人が行方不明などである場合には、相続人の不存在には該当しません。また、相続人はいないけれども、全財産が遺贈(包括遺贈)されている場合も相続人の不存在にあたらないとされています。
相続人のあることが明らかでない場合でも、相続財産はすぐ国のものにはなるのではありません。相続人の相続財産を保全するために、相続人が現れるまで相続財産を管理し、現れなかったときは相続債権者や受遺者に弁済し、特別縁故者に財産分与するなど、利害関係人の利益を図ることを目的として相続財産管理人の制度が設けられています。
相続人が不存在の場合の相続手続きは、次のような流れになります。
(1) 相続財産法人の成立
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされます。
(2) 相続財産管理人の選任申立て
利害関係人(債権者、受遺者、特別縁故者など)から、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てを行います。利害関係人からの請求が無い場合には、検察官が請求します。
(3) 相続財産管理人の選任・公告
請求を受けて、家庭裁判所は相続財産管理人を選任し、その旨を遅滞なく公告します。
(4) 債権者・受遺者に対する債権の申出の公告
(3)の公告後2ヶ月以内に相続人が現れない場合には、相続財産管理人は遅滞なく債権者や受遺者に対して、2ヶ月以上の期間を定めて、債権の請求の申出をするよう公告します。なお、知れたる債権者には個別に債権申出の催告をします。
(5) 債権者・受遺者への弁済
債権の申出期間が満了後、管理人は債権者等へ弁済を行います。
弁済は優先権を有する債権者、一般債権者、受遺者の順に行われ、債権の申出額が相続財産を上回る場合は、配当弁済となります。
(6) 相続人捜索の公告
債権の申出期間が満了後、なお相続人が現れないときは、管理人は(5)の作業と平行して、家庭裁判所に対し相続人捜索の申立てを行います。ただし、弁済で残余財産が無くなった場合には、申立ては必要ありません。
残余財産がある場合、家庭裁判所は申立てに基づき、6ヶ月以上の期間を定めて「相続人捜索の公告」を行います。
なお、(5)の清算後なお残余財産があるときは、その後に現れた債権者等はこの相続人捜索の公告期間内であれば弁済を受けられます。この期間内に相続人としての権利を主張する者が無い場合には、相続人並びに管理人に知れなかった債権者等はその権利を行使できません。
(7) 相続人不存在の確定
(6)の公告期間内に相続権を主張する者がいなければ、相続人の不存在が確定します。
(8) 特別縁故者への相続財産の分与
(6)の公告期間満了後3ヶ月以内に特別縁故者からの請求があった場合、家庭裁判所は、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができます。
特別縁故者に該当するのは、次の者です。
イ.被相続人と生計を同じくしていた者
ロ.被相続人の療養看護に努めた者
ハ.その他被相続人と特別の縁故があった者
つまり、特別の縁故関係があっても申立てをしない限り、相続財産の分与は行われないということです。そして、分与するかしないか、また、一部分与か全部分与かは、家庭裁判所の裁量によります。
また、相続人の捜索の際に、相続人の存在が判明したり、行方不明の相続人がいた場合などは相続人不存在にならないため、その相続人に相続放棄してもらったり、行方不明者の場合は失踪宣告の手続きをしなければ、特別縁故者はそもそも申立てできません。
(9) 相続財産の国庫帰属
(8)で処分されなかった相続財産が、国庫へ帰属します。